院長メッセージ
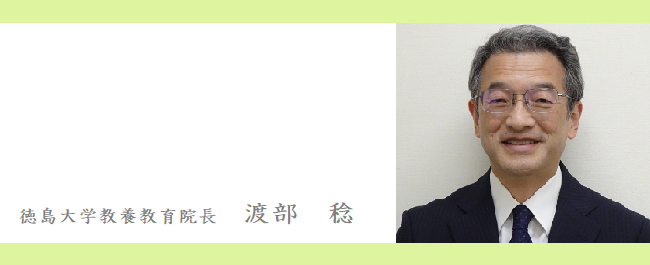
大学での学びは「学修」と記します。中学、高校の「学習」とは何が違うのでしょうか。中学、高校の「学習」では、問題に対してなるべく短時間で正解にたどり着くことを学びます。他方、大学の「学修」では、自分が身に付けた知識を活用して幅広い問題に取り組むことになります。その中には、子供の貧困の問題や少子高齢化、環境問題、ジェンダー間の不平等など、明確な正解のない問題もあるでしょう。また、大学では自ら主体的に学び行動することも求められます。徳島大学に入学したみなさんには、高校までの「学習」から大学の「学修」へスムーズな切り替えができるよう、大学がさまざまな教育を準備しています。
大学での教育は、1年次の「教養教育」、2年次以降の「専門教育」に大きく分けることができます。もちろんこれは厳密なものではなく、1年生のうちから「専門教育」も受講しますし、高学年での「教養教育」もあります。「専門教育」とは、みなさんが所属する学部・学科の特性に応じた専門的な教育です。それに対し「教養教育」では、学部の垣根を超えた幅広い学問領域を学びます。例えば医学部のみなさんも「教養教育」で文学や歴史の授業を受講することもあるでしょう。また体育(ウェルネス)の授業も受講することができます。
私は理学部の出身です。当時は教養教育を専門に行う教養部と呼ばれる組織が大学にあり、私はそこで1年半の教養課程を過ごしました。大学に入学するとすぐに専門の授業が始まると思っていたのですが、1年半の間は専門とはあまり関係のないような社会学や心理学、文学、語学の授業を受講しました。最初はなぜ理学部の自分がこのような授業を受けるのだろうと思いましたが、すぐにそれらの授業に引き込まれました。私はもともと読書が好きだったのですが、教養の授業で今まで読んだことの無かった作家・作品に接することができました。また社会学や倫理学も学んで、自分自身でも知らなかった自分の興味に気が付くこともできました。教養の授業が無ければ、私はこのような幅広い領域の学問を学ぶことはなかったと思います。
徳島大学では、平成28年に大学の教養教育を取りまとめる組織として「教養教育院」が作られました。徳島大学の教養教育は教養教育院が中心となって行われていますが、実際にはいろいろな学部の教員が授業担当者として参加しています。さまざまなバッグラウンドを持った授業担当者からの幅広い学問領域の授業を受講し、自ら主体的に学ぶことで、広い知識と視野を身に付け、俯瞰的に物事を捉えることができるようになるでしょう。ちょうど広大なすそ野を持つ富士山が日本で一番高い山であるように、広い学問領域の土台を持ってこそ、後の専門教育で高い専門性を持った学修が可能になります。
新入生のみなさんが、徳島大学の教養教育で知識の幅を拡げ、自分の新しい可能性に気づき、主体的な学修習慣を身に着けることができれば、こんなに嬉しいことはありません。みなさんの目の前には、素晴らしい未来が待っています。その未来をさらに輝かしいものにするためにも、徳島大学で意欲的に学修に取り組んでいただければと思います。頑張ってください。期待しています。

